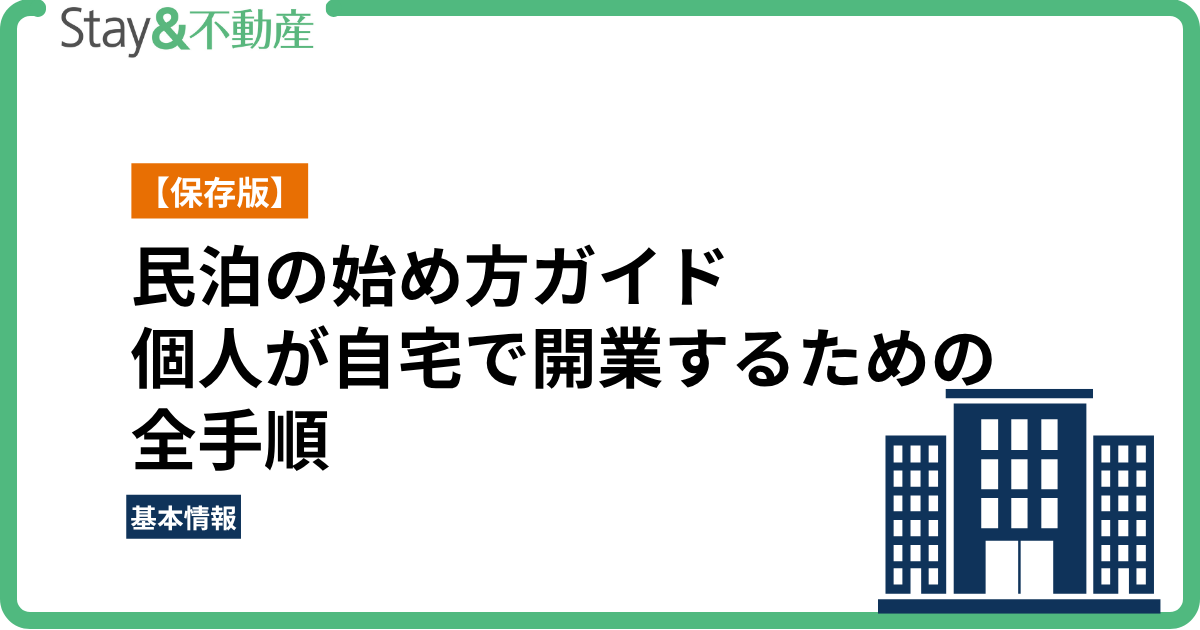「民泊を自宅で始めたいけれど、何から始めればいいか分からない…」
そんな方に向けて、法律の基礎知識から具体的な手順、初期費用、注意点までを網羅的に解説します。
この記事を読めば、個人が自宅で合法的に民泊をスタートするために必要なすべてがわかります。
民泊を自宅で始めるには?|この記事の結論
✔ 民泊は自宅でも合法に始められる
民泊と聞くと、「ホテルのように施設を構えて営業しないといけないのでは?」と思う方も多いかもしれませんが、実はあなたの自宅や空き家でも合法的に民泊を始めることができます。
✔ 初期費用・手続き・注意点を理解すれば誰でも参入可能
民泊には法律や届出、設備要件など最低限のルールがありますが、それをきちんと押さえれば、個人でも無理なくスタートできます。
特別な資格や法人登録も不要で、フリーランスや副業として始める方も増えています。
✔ 年間180日以内なら副業にもおすすめ
民泊新法に基づいて運営すれば、営業は年間180日までに制限されるものの、副業としての収益源には十分な可能性があります。
特に観光地やアクセスの良いエリアに住んでいる方にとって、自宅の一部を活用する民泊は魅力的な選択肢です。
そもそも民泊とは?|法律・種類・制度の違いをわかりやすく解説

民泊とは、住宅(戸建てやマンションなど)を活用して、旅行者や出張者などに短期間の宿泊サービスを提供する形態のことを指します。
Airbnb(エアビーアンドビー)などの民泊仲介サイトを通じて、個人が自分の家の一部や空き家を貸し出すというスタイルが主流です。
ホテルや旅館との違いは「営業の仕組み」と「施設の規模」です。ホテルは旅館業法の許可を取得し、常時営業を前提としています。
一方で、民泊は年間の営業日数が制限されていたり、住宅を活用することでより簡易に始められるという特徴があります。
2.民泊新法・特区民泊・旅館業法の違い
民泊と一口にいっても、運営方法には3つの制度があります。それぞれの特徴は以下の通りです。
- 民泊新法(住宅宿泊事業法):最も一般的で、年間180日以内の営業が可能。届出制で運用もシンプル。個人の副業に最適。
- 特区民泊:一部の自治体(例:大阪市、東京都大田区など)で認められている。条件として2泊3日以上の滞在が必要。
- 旅館業法:ホテル・簡易宿所など、常時営業を前提とした業態。許可取得が必要でハードルはやや高め。
この記事で主に取り上げるのは、最もハードルが低く、個人に適している「民泊新法」による運営です。
3.個人が使うべき制度は「民泊新法」でOK
結論からいえば、これから民泊を始める個人の多くは「民泊新法」一択です。
届出制なので手続きも比較的簡単で、必要な設備や書類もそこまで複雑ではありません。
また、自宅を一部貸す「家主居住型」のスタイルであれば、ゲストとのトラブルも起きにくく、運営の不安も少ないでしょう。
一方で、「家主不在型」の場合は住宅宿泊管理業者への委託が義務付けられるので、その点だけ注意が必要です。
自宅で民泊を始める6つのステップ

ここからは、実際に自宅で民泊を始めるために必要な流れを6ステップで解説していきます。
初めての方でも迷わず実行できるように、1つひとつ具体的に紹介します。
ず最初に確認すべきなのは、自宅や保有している物件が民泊に使えるかどうかです。
民泊新法に基づく運営では、以下のような条件を満たす必要があります。
- 生活に必要な設備(キッチン、トイレ、浴室、洗面所)がある
- 居住実績がある、もしくは居住可能な状態にある
- 用途地域が「住居系」や「商業系」で、条例で民泊が禁止されていない
特に都市部では条例によって営業日数が制限されている場合もあるので、必ず自治体のルールを確認しておきましょう。
次に、宿泊者が安心して滞在できるように最低限の設備を整えます。
民泊で必要とされる主な設備は以下の通りです。
- キッチン(コンロ・冷蔵庫など)
- 浴室(シャワーまたはバスタブ)
- トイレ・洗面所
- 消火器・火災報知器・非常灯などの消防設備
消防設備の設置については、専門業者に依頼するのが一般的です。
特に自動火災報知器は、設置工事が必要になることもあるため、早めの準備をおすすめします。
設備が整ったら、次は管轄の保健所や自治体へ「住宅宿泊事業の届出」を行います。
民泊新法に基づく営業では、以下のような書類が必要です。
- 住民票や身分証明書
- 建物の図面や間取り図
- 使用承諾書(賃貸物件の場合は大家の許可)
- 消防設備に関する証明書
オンライン申請が可能な自治体も増えており、国土交通省の「民泊制度運営システム」から届出が可能です。
審査が通れば、晴れて合法的な民泊運営がスタートできます。
申請が通ったら、いよいよ内装の準備です。
以下のような家具や家電は、最低限揃えておきましょう。
- ベッドまたは布団、寝具一式
- エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ
- テーブル、イス、カーテン、照明
- リネン類(タオル、シーツ、布団カバー)
- 掃除用具、ゴミ箱、アメニティ類
設備は新しいものを買う必要はなく、中古品やリースを活用してコストを抑えるのも一つの手です。
ただし、清潔感と安全性は必ず確保してください。
準備が整ったら、集客のために民泊プラットフォームへ登録しましょう。
おすすめは以下の3つです。
- Airbnb:世界最大の民泊サイト。利用者数が圧倒的。
- Booking.com:ホテル利用者にも訴求できる。
- 楽天ステイ:日本国内の利用者に強い。
登録時には、物件の魅力を伝える写真や説明文が重要です。
プロのカメラマンに撮影を依頼することで、予約率が大きく向上するケースもあります。
よいよ民泊の営業開始です!ただし、始めて終わりではありません。
民泊新法では、以下のような報告義務があります。
- 宿泊者数・宿泊日数・国籍別の内訳
- 2ヶ月に1度、自治体への報告(Web提出が可能)
また、ゲストからの問い合わせ対応、清掃業者の手配、レビュー管理など、日常的な運営業務も発生します。
必要に応じて民泊運営代行サービスを活用するのもおすすめです。
民泊の初期費用・運営費用のリアル

民泊を始めるにあたって、多くの人が気になるのが「結局いくらかかるの?」という点ではないでしょうか。
ここでは、実際の初期費用の内訳と、できるだけコストを抑える方法を紹介していきます。
1.平均初期費用はいくら?相場と内訳
自宅を利用して民泊を始める場合、初期費用の平均相場は約50万〜100万円です。
ただし、これは物件の状態やどこまで設備投資を行うかによって上下します。
主な費用項目は以下の通りです。
- 家具・家電の購入:20万円〜30万円程度(中古品利用で抑えられる)
- リネン・清掃道具:2万円〜5万円
- 消防設備設置費:約20万円(物件によってはもっと高額になるケースも)
- 届出・申請手数料:数千円(行政書士に依頼する場合は+20万〜30万円)
すでに住んでいる自宅を使う場合は、大掛かりなリノベーションが不要なため、大幅に費用を抑えることができます。
逆に空き家をフルリフォームして民泊用に整える場合は、100万円を超えることも珍しくありません。
2.節約するためのポイント3選
なるべく費用を抑えて始めたいという方に向けて、コストダウンのコツを3つ紹介します。
- 家具・家電は中古を活用
メルカリやジモティー、リサイクルショップなどを活用することで、必要な家具や家電を新品の半額以下で揃えることができます。 - DIYで設備を整える
ちょっとした棚の設置や装飾は、自分で行えば業者に頼むよりも格段に安く済みます。YouTubeなどを活用してDIYもおすすめ。 - 自治体の補助金制度を活用
一部の自治体では、空き家の活用や観光振興のために、民泊開業者向けの補助金や助成金を用意しているところもあります。
3.行政書士・清掃業者に依頼する場合の料金
届出や書類作成が面倒に感じる方は、行政書士に依頼するのも選択肢のひとつです。その場合、相場は20万円〜30万円前後。
また、運営後の清掃をプロに委託する場合、1回あたりの清掃費用は5,000円〜1万円ほどが目安です。
民泊専門の清掃代行業者と契約することで、リネン類の補充やレビュー対応までまとめて任せることも可能です。
こうした外注コストも踏まえた上で、あらかじめ収支シミュレーションを行っておくことが重要です。
個人宅で民泊を始めるときの注意点と落とし穴

民泊は自宅でも始められる手軽なビジネスですが、実は思わぬ落とし穴も存在します。
事前に知っておくことで防げるリスクばかりなので、必ずチェックしておきましょう。
1.地域の条例・用途地域の確認
民泊新法(住宅宿泊事業法)では、全国どこでも民泊ができるわけではありません。
自治体ごとに定められた条例や用途地域の規制があるため、最初に確認しておくことが必須です。
例えば、東京都新宿区では住居専用地域における民泊営業は制限されていますし、大阪市では特定の曜日や時間帯に営業を制限しているケースもあります。
用途地域とは、都市計画法に基づいて地域に割り振られた「土地の使い道」のこと。
民泊が許可されている地域かどうかを、市区町村の都市計画課で確認しておきましょう。
2.住宅ローン控除が使えなくなる可能性
もしあなたの家が住宅ローン控除を受けている最中であれば注意が必要です。
住宅ローン控除は「自分が居住する住宅」であることが条件。民泊として貸し出す部分が大きくなると、控除対象外になる可能性があります。
1室だけの貸し出しであれば問題にならない場合もありますが、念のため税務署や金融機関に事前に相談しておくのが安心です。
3.賃貸住宅・マンションは管理規約に注意
賃貸物件や分譲マンションの場合は、大家さんや管理組合の許可が絶対に必要です。
管理規約で「居住以外の目的での使用を禁止」とされているマンションでは、民泊営業は認められていません。
無断で始めると即契約解除やトラブルの原因になるので、必ず事前に管理規約を確認しましょう。
4.近隣トラブル・騒音リスクの予防策
民泊において一番多いクレームが「騒音」と「ゴミ出し」です。
ゲストが外国人や観光客であれば、生活リズムや文化の違いもあり、トラブルに発展しやすくなります。
以下のような対策を講じておくと安心です。
- ハウスルールを英語・日本語で明示する
- チェックイン時にゴミ出し・騒音の注意を伝える
- 近隣住民へ事前に説明・挨拶を行う
- トラブル発生時の緊急連絡先を用意しておく
信頼を失ってからでは遅いので、予防策はしっかりと。
5.保険に入るべき?民泊保険の基礎知識
民泊中に事故や損害が発生する可能性もゼロではありません。
ゲストが設備を壊したり、火災・水漏れといった事態が起こった場合、補償できるように民泊対応の保険には必ず加入しておきましょう。
通常の火災保険ではカバーされないケースもあるため、以下のような保険を検討してください:
- 民泊専用損害保険(東京海上日動や損保ジャパンなど)
- Airbnbホスト保証(最大1億円補償)
- 住宅総合保険に特約を追加
「まさか」のトラブルから自分を守るためにも、保険の準備は必須です。
【体験談】自宅を活用した民泊成功事例

ここでは実際に、自宅を使って民泊を始めた個人のリアルな成功事例をご紹介します。
環境や条件は人それぞれですが、きっとあなたのヒントになるはずです。
地方在住主婦が月10万円稼ぐまでの流れ
神奈川県の郊外に住む40代の主婦Aさん。子育ても一段落し、何か収入を得られることができないかと探していた中、目をつけたのが「自宅の空き部屋での民泊」でした。
もともと使用していなかった2階の和室を、簡単なリフォームと家具の購入でゲストルームに改装。エアコンやWi-Fiを整備し、Airbnbに登録。営業日は月10日ほどに絞って無理なく運営を開始しました。
宿泊者の多くは外国人旅行者で、「本物の日本の家庭に泊まれる」と好評。レビューも順調に集まり、開業3ヶ月後には月10万円を安定して稼ぐように。
「最初は不安だったけど、ゲストと交流もできて楽しいし、空き部屋が収入源になるなんて想像もしなかった」と語っています。
会社員が副業で始めて法人化したケース
東京都在住の30代男性Bさんは、サラリーマンとして働く傍ら、副業として民泊を開始。祖父母から相続した埼玉県の空き家を活用しました。
開業前に100万円ほどかけて水回りをリフォームし、消防設備も設置。最初は自分で予約管理や清掃を行っていましたが、徐々に稼働率が上がり、代行業者に外注するように。
2年目には月の売上が30万円を超え、本業の収入を上回る月も。法人を設立して事業として本格的に展開し、現在では複数の物件を管理する小規模な民泊事業者として独立。
「最初の一歩は大変でしたが、継続すればスケールできる。自宅や空き家という資産が収益を生むことに気づけたのは大きかった」と振り返ります。
よくある質問・不安に対するQ&A
ここでは、「民泊を自宅で始めたい」と考えている方からよく寄せられる質問をピックアップし、分かりやすく回答していきます。
まとめ|民泊は個人でも自宅から始められる副業
民泊は今や、法人だけのビジネスではありません。正しい手続きを踏めば、個人でも合法的に、しかも自宅から始めることができます。
この記事では、「民泊 始め方 個人 自宅」というテーマで、
- 民泊の種類と法制度
- 開業までの6ステップ
- 初期費用と節約ポイント
- 注意点とリスク対策
- 税金・確定申告の基礎知識
- 実際の成功事例
まで、網羅的にご紹介してきました。
もし「今の自宅を有効活用したい」「副業として収入を増やしたい」「空き部屋を眠らせたままにしたくない」と考えているなら、民泊は非常に現実的な選択肢です。
最初の一歩を踏み出すのは勇気がいりますが、しっかり情報を集め、準備を整えれば、誰でも安心して始められます。
この記事が、あなたの民泊デビューの後押しになれば幸いです。
まずは、空き部屋の写真を撮ってみるところから、始めてみませんか?