首都圏でマンション価格が値上がりし続けている今、購入や売却を検討する方にとって「いつまで価格が上がり続けるのか?」は大きな関心事です。
マンション値上がりの背景には物価高や金利政策、供給不足など複数の要因が絡んでおり、今後の市場動向を正確に見極めることが重要です。
本記事ではマンションの値上がりがいつまで続くのか、今後の価格推移予測と共に、買い時・売り時のポイントを徹底解説。リスクを抑えた資産運用に役立つ情報をお届けします。
マンション価格が高騰している理由とは?

現在、マンション価格の値上がりが続いており、都心部では平均価格が8,873万円にも達したことで、価格上昇がいつまで続くのか、多くの人が関心を寄せています。
さらに、建築コストの値上がりも影響を及ぼし、マンション購入を検討する方にとっては、今後の値動きが大きな関心事でしょう。以下でマンション価格上昇の要因をチェックしましょう。
- 物価上昇と建築コストの影響
- 供給不足と需要増加の背景
- 金利政策と市場動向の関係性
物価上昇と建築コストの影響
マンション価格の値上がりがいつまでも続く要因のひとつに、物価上昇と建築コストの増加が挙げられます。近年、資材の値上がりや人件費の増加により、建築費用が大幅に上がり、結果として新築マンションの販売価格も上昇しています。特に都心部や人気エリアでの値上がりがいつまでも顕著です。
1. 建築資材の値上がり
コロナ禍以降、世界的に物流が混乱し、資材の供給不足が問題となっています。鉄鋼やコンクリートなどの基本資材に加え、エネルギー価格の上昇も建築コストに影響を及ぼしており、特に日本国内の建設プロジェクトでは予算が大幅に増加しています。下記は主要な建築資材と、その価格変動を示す表です。
| 資材 | 2020年価格 | 2023年価格 |
|---|---|---|
| 鉄鋼 | 100万円 | 150万円 |
| コンクリート | 50万円 | 75万円 |
| 木材 | 80万円 | 120万円 |
| ガラス | 60万円 | 90万円 |
資材価格が軒並み50%づつほど上昇していることにより、施工費の大幅な値上がりがマンション価格に影響し、購入希望者にとってはさらなる負担が増す結果となっています。この傾向はいつまで続くか、判断が難しいところです。
2. 人件費の増加
少子高齢化により、建設業界では労働力不足が深刻化しています。
人件費が上昇することで、マンションの建設費用が増加し、結果として販売価格にも反映されています。これによっても、新築マンションの価格は上乗せとなっています。建築費同様、人材不足がいつまで続くかは未知数でしょう。
3. 土地の仕入れ値
土地の仕入れ値の要因により、マンションの値上がりはあと数年は続くと予想されています。
これまで金融緩和の政策によって低利の融資が続き、不動産市場に流れた資金で土地が買われました。これらの土地にマンションが建設されて販売された分までは、土地値上がりの影響を受けた販売価格が継続します。この影響が終わるまでに、まだ時間がかかるといわれているのです。
供給不足と需要増加の背景
マンション価格の値上がりがいつまでも続く背景には、供給不足と旺盛な需要増加が関係しています。
特に都市部での需要が集中しているため、供給が追いつかず、マンション価格が過去10年で2倍以上にまで値上がりしている地域もあります。こうした需給のアンバランスが生じた理由は、人口の都市集中とともに、住宅開発に関わる課題が絡み合っているためです。
1. 都市部への人口集中と需要の拡大
都市部では仕事や生活の利便性を求める人が増加し、特に首都圏や大都市でのマンション需要が大きく伸びています。都市部における生活環境の充実や交通インフラの整備が進む中で、若い世代からシニア層まで、幅広い層がマンション購入を希望しています。
2. 新規供給の減少
建築コストの上昇や土地取得の難しさも、マンションの供給不足の一因となっています。
以下の表は、主要都市におけるマンション供給戸数の推移を示しています。
| 年度 | 東京 | 大阪 | 名古屋 | 福岡 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 50,000戸 | 30,000戸 | 15,000戸 | 10,000戸 |
| 2018年 | 45,000戸 | 28,000戸 | 13,000戸 | 9,000戸 |
| 2023年 | 40,000戸 | 25,000戸 | 12,000戸 | 8,500戸 |
供給戸数が減少していき供給不足がいつまでも続く中、需要は引き続き高いため、マンション価格は上昇傾向にあります。
3. マンション価格の値上がりは「いつまで」続くのか?
このような供給不足と需要のバランスが崩れた状況では、マンション価格が「いつまで」上がり続けるのかについて関心が高まります。
現時点では価格が大幅に下がる兆しは見られません。
金利政策と市場動向の関係性

マンション価格の値上がりがいつまでも続く要因には、金利政策と市場動向も大きく影響しています。低金利政策により住宅ローンの負担が軽減され、多くの人がマンション購入を検討しやすい環境が整いましたが、同時にこれが価格上昇の一因となっています。
1. 低金利政策と住宅ローン需要の増加
日本は長らく低金利政策を維持しており、住宅ローン金利も歴史的に低い水準にあります。
このため、ローンを利用してマンションを購入する人が増加し、需要が上昇しています。低金利による支払い負担の軽減は魅力的ですが、同時に不動産市場への資金流入を促進し、土地価格の高騰を進めてきました。
2. 金利上昇の可能性と市場への影響
金利は今後上昇するというのが定見となりましたが、景気が上向かない限りは、本格的な利上げは行われないでしょう。
今後の金利政策の変動がどのようにマンション市場へ影響を及ぼすかが注目されています。以下に、金利の上下が市場に影響を与える影響を比較してみます。
| 金利水準 | マンション需要への影響 | 価格への影響 |
|---|---|---|
| 低金利(現状) | 購入需要が高まる | 価格は上昇傾向を維持 |
| 中金利(小幅上昇) | 需要がやや減少、投資家の慎重な判断が増加 | 価格の上昇が鈍化し、安定に向かう可能性 |
| 高金利(大幅上昇) | 住宅ローンの負担増加で購入者が減少 | 価格の下落または安定化の可能性 |
このように、金利が上昇すると購入者にとってローンの負担が増え、マンション需要の減少や価格の安定化につながると予想されます。しかし、現状では低金利政策の影響が続いています。
3.外国人投資家の参入と需給バランスの変化
日本の不動産市場は、特に都市部において外国人投資家の関心が高まっています。
低金利政策と安定した市場環境が、国内外の投資家にとって魅力的であり、この資金の流入がマンション需要を押し上げる要因の一つとなっています。特に東京や大阪といった主要都市では、需要の高まりが価格上昇につながり、結果として日本人の購入者にとって手が届きにくい状況を生んでいます。
マンション値上がりの現状

マンションの価格は平成初期の1992年からの10年間で下落が続きました。しかしそこで底を打ったあとは、リーマンショックや円高不況、コロナ禍で多少の下降に転じた時期以外は、再び上がり続けています。
中でも過去10年で大幅に上昇し、中古マンションでも値上がり傾向が続いています。首都圏のマンション価格は、2002年頃の最低の状態から2倍近くとなり、バブル期の水準に近づいてしまいました。
新築マンションの価格推移
新築マンションの価格は近年、値上がりが顕著です。特に都市部における新築マンション価格は、過去10年で大きく上昇しており、これは物価上昇や建築コスト、さらに金利政策の影響を受けているためです。
東京や大阪といった主要都市では、平均価格が1億円近くに達する物件もあります。
新築マンション価格の推移を都市ごとに見てみましょう。
| 年度 | 東京平均価格 | 大阪平均価格 | 名古屋平均価格 | 福岡平均価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 5,500万円 | 4,000万円 | 3,800万円 | 3,200万円 |
| 2018年 | 6,800万円 | 5,200万円 | 4,600万円 | 4,000万円 |
| 2023年 | 8,873万円 | 6,500万円 | 5,800万円 | 5,000万円 |
このように、東京を中心に各都市で新築マンションの平均価格が上昇しているのがわかります。
現時点では、あと2~3年は値上がりが続くと予測されていますが、好立地のマンション敷地が払底し、今後資産価値に見合うか疑問視される分譲も出てきているのが現状です。新築マンションの購入を検討する際には、こうした要因を総合的に判断し、冷静に検討しましょう。
中古マンションの価格推移
中古マンションの価格も新築と同様に値上がりが続いており、需要が増加している背景にはさまざまな要因があります。新築マンションの価格が値上がりしていることから、中古マンションへの関心が高まり、物件数が限られる中で需要と供給のバランスが崩れた結果、価格が上昇しています。
近年の主要都市における中古マンション価格の推移を確認すると、下記のような上昇が見られます。
| 年度 | 東京平均価格 | 大阪平均価格 | 名古屋平均価格 | 福岡平均価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 3,500万円 | 2,800万円 | 2,500万円 | 2,200万円 |
| 2018年 | 4,200万円 | 3,400万円 | 3,100万円 | 2,700万円 |
| 2023年 | 5,000万円 | 4,200万円 | 3,800万円 | 3,300万円 |
新築マンションと比べ、物件が限られる中古市場では需要が供給を上回る傾向にあり、価格の値上がりが続いています。
特に築浅物件やリノベーション済みの物件は人気が高く、値上がりしています。また、中古物価は立地や利便性が高いものが多いため、都市部の中古マンションには高い需要が集まっています。
中古マンション価格は今後も新築の値動きに合わせて値上がりが続くと予測されていますが、注意すべき点は、修繕などの管理体制が充分でない物件を高価で購入することです。
購入検討者は、居住してからの維持費用を意識しながら、中古マンションの購入を考えることが重要です。
マンション価格の値上がりはいつまで続くか?:予測される今後の価格変動

専門家によると、マンション価格の値上がりはいつまで続くのか、多くの要因が絡んでいるため一概には言えませんが、少なくとも数年間は上昇が続く可能性が高いと見られています。
この値上がりの背景には、アベノミクス政策による経済刺激策の影響が根強く残っている点も挙げられます。2010年代初頭に始まったアベノミクスは、金融緩和を通じて不動産市場にも波及効果をもたらし、マンション価格が上昇傾向に転じました。そしてその影響は一定のタイムラグを伴って続いています。
アベノミクスと値上がりのタイムラグ【いつまで?】
アベノミクス政策によって低金利が長期にわたって維持され、投資家や富裕層を中心にマンション市場への関心が高まりました。
金融緩和が進むとともに、建築コストや人件費の上昇も追い風となり、新築・中古マンションの両方で価格が上昇し始めました。この政策の効果が完全に薄れるにはまだ時間がかかるため、現在の値上がりはまだ続く可能性があると予測されています。
土地の仕入れ値
土地の仕入れ値の要因により、マンションの値上がりはあと2~3年は続くと予想されています。
これまで金融緩和の政策によって低利の融資が続き、不動産市場に流れた資金で土地が買われました。これらの土地にマンションが建設されて販売された分までは、土地値上がりの影響を受けた販売価格が継続します。この影響が終わるまでに、あと2~3年はかかるといわれているのです。
金利は下がるのか?
専門家は今後の金利動向もマンション価格のカギを握るとしています。
仮に金利が引き上げられる場合、住宅ローンの返済負担が増加し、購入者が減少することで価格が安定または下落に転じる可能性もあります。
特に高金利になると、マンション価格の値上がりが収束し、逆に価格が下がる可能性もあり得ます。
エリア別のマンション価格動向と注目の地域
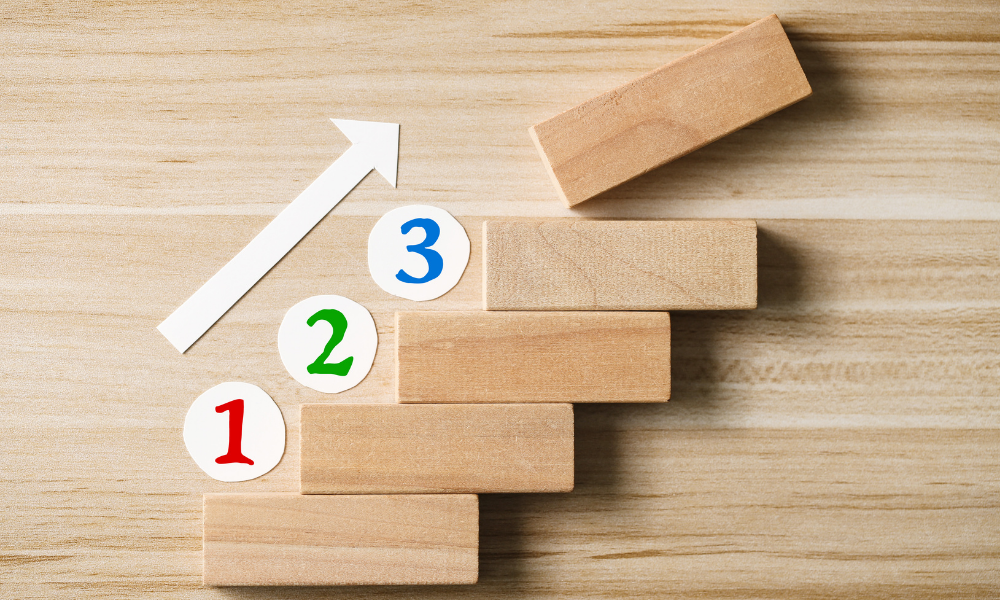
マンション価格の値上がりは全国で見られる現象ですが、エリアによって上昇率や需要の差が見られます。特に都市部の人気エリアでは顕著な値上がりが続いており、価格が「いつまで」上がり続けるのか、多くの関心が集まっています。
東京・首都圏
首都圏は依然として需要が高く、特に東京23区の一部では供給不足も重なり、価格が急上昇しています。東京の中心地である千代田区や港区、渋谷区などのマンションは、立地の利便性とブランド力が影響し、値上がり率が他エリアより高い傾向にあります。一方、周辺の郊外エリアでも価格が上昇しており、今後も需要が続くと見られています。
| エリア | 2013年平均価格 | 2023年平均価格 | 値上がり率 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 7,000万円 | 12,000万円 | 71.4% |
| 港区 | 8,500万円 | 15,000万円 | 76.5% |
| 渋谷区 | 6,800万円 | 11,500万円 | 69.1% |
大阪・関西圏
関西圏では、大阪市内のマンション価格が値上がりしています。特に梅田・新大阪エリアや難波周辺は商業施設が集まり、住環境が整っていることから需要が増加。近年、海外からの投資も影響し、価格上昇が続いています。
名古屋・中部圏
中部圏では、名古屋市内のマンション価格が安定的に上昇しているものの、東京や大阪に比べると比較的緩やかなペースです。しかし、名古屋駅周辺や栄地区は今後も注目されるエリアとして人気が高く、引き続き価格が上昇する可能性があります。
福岡・九州圏
福岡市は九州の経済中心地であり、交通アクセスの良さや住環境の向上により、マンション需要が高まっています。特に博多や天神周辺では価格が急上昇し、国内外からの投資も流入しています。福岡市内のマンション価格は今後も値上がりが続くと予想されています。
価格が安定・下落するタイミングの兆し

マンション価格が安定、または下落に転じる可能性があるのは、前述のように物価上昇の鈍化や金利上昇、供給が増加する場合です。特に金利政策の影響で住宅ローン金利が上がれば、購入希望者の需要が減少し、価格が安定に向かう可能性があります。
住宅市場の資金
マンションの値上がりがいつまでも続く背景には、住宅市場への豊富な資金供給が影響しています。低金利政策の影響を脱し、金利が上昇に向かって舵を切れば、マンション価格は自然に下降に向かいますが、現在の景気動向では、難しいとみるのが一般的です。
1. 住宅ローンと資金の流入
現在、低金利政策が長期にわたって続いていることで、住宅ローンが非常に利用しやすい環境にあります。これにより、多くの人がマンション購入に資金を投入し、需要が高まっています。特に、都市部や人気エリアではこの資金流入が集中しているため、マンション価格の値上がりが加速しています。
2. 資金流入が価格に与える影響
住宅市場への資金流入は、マンションの価格を引き上げる大きな要因のひとつです。新築や中古マンションへの需要が高まり、供給が追いつかない状況が続いているため、価格は上昇傾向にあります。特に東京、大阪、福岡などの都市圏で顕著に値上がりが進んでいます。
以下は、住宅ローン残高の推移を示す表です。金融機関は既存の多数の高利住宅ローンが完済する時期に差し掛かっており、物件不足と相まって「まだまだ貸します」の姿勢が崩せない状況なのです。
| 年度 | 全国住宅ローン残高(兆円) | 年間増加率 |
|---|---|---|
| 2015 | 60 | 3.5% |
| 2018 | 65 | 4.2% |
| 2021 | 72 | 5.1% |
| 2023 | 78 | 4.7% |
3. 投資資金の流入とマンション価格
さらに、個人投資家や企業が資産運用の一環としてマンション市場に参入している点も価格上昇を支えています。
特に低金利環境下で、他の金融商品と比較して安定したリターンが期待できる不動産への投資が人気です。この資金流入の影響が「いつまで」続くかに関心が集まるのは、将来の価格変動を見極める上でも重要です。
金利の動向
マンション価格の値上がりがいつまでも続く中で、金利の動向も価格の行方を左右する重要な要因です。
日本は長年にわたり低金利政策を続けており、この影響で住宅ローン金利も非常に低く、多くの人がローンを利用してマンション購入に踏み切りやすい環境にあります。
1. 低金利政策と住宅ローン
日本の低金利政策は、経済刺激策の一環として導入され、住宅ローンの金利を歴史的な低水準に抑えています。これにより、マンション購入者の月々の返済負担が軽減され、購入希望者が増加しました。
現状バブル全盛期の頃と変わらない水準の価格でも、金利が安いことで返済額は半額程度で済むため、購買意欲も融資の意欲も盛んな状態です。
2. 今後の金利上昇の可能性
低金利が続いていますが、今後の経済状況やインフレの動向によっては、金利が引き上げられる可能性もありえます。円安を防ぐなどの政策的な意図からです。
金利が上昇すると、住宅ローンの返済負担が増加し、マンションの購入を控える人が増える可能性があります。これにより、マンションの価格が安定する、あるいは下落に転じると考えられます。
以下は、住宅ローン金利が変動した場合の購入負担の変化を示す表です。
| 金利水準 | 月々の返済額(3000万円借入、35年ローンの場合) |
|---|---|
| 0.5% | 約8.4万円 |
| 1.0% | 約9.1万円 |
| 1.5% | 約9.8万円 |
| 2.0% | 約10.6万円 |
このように、金利が上がることで月々の返済額も増加し、購入者にとっては大きな負担増となります。
ただし購入後に上昇した変動金利は、5年間は反映されず、反映後も返済総額の25%を超えないという、「5年ルール」「25%ルール」を採用する金融機関が多いです。
3. 政策金利の動向
将来的にローンの金利が上がるかは今後、政府日銀が短期プライムレートの利上げなど、金融緩和の縮小を進めるかにかかっています。
金融引き締めの方針で2024年10月、短期政策金利の利上げが発表されましたが、その後は利上げを凍結した形になっています。
ただし前述のように金融引き締めの政策がマンション価格に反映されるためには2年強のタイムラグがあることも、ご承知おきください。
価格上昇中の「買い時」を見極めるためのポイント

マンションの値上がりがいつまでも続く中で、「買い時」を見極めることは難しい判断です。
物価上昇、供給不足、低金利政策といった要因が相まって価格が上昇していますが、いつまでこの上昇が続くかは見通しがつきにくい状況です。しかし、将来的な金利上昇や供給の増加が見込まれる際には、今の「買い時」を慎重に判断するポイントになります。
現在の市場状況を見極める
まず、マンション価格がどれだけ上昇しているかを理解することが重要です。下記のように都市部のマンション価格は過去10年で大幅に上昇しています。
| 年度 | 東京平均価格 | 大阪平均価格 | 名古屋平均価格 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 5,500万円 | 4,000万円 | 3,800万円 |
| 2023年 | 8,873万円 | 6,500万円 | 5,800万円 |
このように価格が高止まりしている現状では、購入タイミングを見極める際に、金利や供給の動向にも注目する必要があります。しかし、手に入れたい物件の立地にこだわる場合、いつまでではなく今が買い時という見方も成立するのです。
低金利を活用する
現在の低金利政策は、住宅ローンの負担を軽減しているため、購入検討者にとってはメリットのある環境です。
低金利が続いている間は月々の返済負担が軽く、将来の金利上昇リスクを踏まえても比較的安心して購入に踏み切れる時期と言えます。つまり低金利の恩恵を受けられる今は買い時のひとつとも考えられます。
長期的な視点での資産価値を考える
マンション購入は長期的な投資と考えた場合、今の価格上昇期に購入することが適切かを見極めることが重要です。
都心部のマンションであれば資産価値が下がりにくいため、いつまで値上がりしていても長期的に見て安定的な価値を保つ可能性があります。立地条件や築年数なども考慮し、資産価値が維持されやすい物件を選ぶことで、将来的な値上がりに対するリスクを抑えることができます。
将来のリスクに備える「売り時」を見極めるためのポイント

マンション価格の値上がりが続いている中で、「いつまで」この上昇が続くのかは、不透明といわざるを得ません。適切な「売り時」を見極めるためには、立地や市場動向、残債割れのリスクなどを考慮することが重要です。
立地の重要性
マンションの立地は資産価値の維持に大きく影響します。都心部や交通利便性の高いエリア、商業施設が充実した地域の物件は、他のエリアと比べて価格が安定しやすい傾向にあります。
将来の売却を考える際には、こうした「立地」の条件が良い物件ほど、売却時のリスクを抑えやすく、価格の暴落に備えることができます。
マーケットの動向と金利の影響
金利の上昇や経済情勢の変化はマンション市場に直接的な影響を与えます。市場の値上がりが「いつまで」続くかに不安を感じる場合、低金利が続いている現状のうちに売却を検討することも有効です。
将来の残債割れのリスク
将来、マンション価格が下落して残債割れが発生する可能性も考慮する必要があります。残債割れとは、マンションの売却価格が住宅ローン残高を下回り、売却しても借金が残ってしまう状態を指します。このリスクを回避するため、購入から数年後、価格が安定しているタイミングでの売却を視野に入れることが大切です。
周辺エリアの再開発や将来の需要予測
立地条件が良いマンションでも、周辺エリアの状況変化によって資産価値が影響を受けることがあります。
再開発が進むエリアは将来的な需要が高まるため、売却時の価値も期待できますが、逆に開発計画が停滞したり、人口減少の影響が懸念されるエリアはリスクが生じやすくなります。
| 判断基準 | チェックポイント |
|---|---|
| 立地 | 交通利便性、周辺施設の充実、都市部かどうか |
| 市場動向 | 金利の上昇リスク、経済の先行き |
| 残債割れのリスク | 売却時にローン残高を上回るかの確認 |
| 将来の需要予測 | 周辺エリアの再開発や人口動向 |
長期的な市場予測に加え、今後の価格の変動に備え、将来の売却リスクを抑えた計画を立てることが賢明です。
まとめ

マンション価格の値上がりが続く中、今後の市場動向や価格の変動を見極めることは、購入・売却の判断において重要です。値下げに向けた指標は把握したうえで、いつまでの値上がりか、動向をしっかり見極めておくことが大切です。
現在は物価上昇や供給不足、低金利政策などが価格上昇の要因となっていますが、今後の金利動向や供給増加の影響により、安定・下落のタイミングが訪れる可能性もあります。
特に首都圏の価格変動を踏まえ、適切な「買い時」「売り時」を見極め、長期的な視点でリスクを抑えた判断をすることが大切です。
売り時を逃さない適切なサポートは、Stay&不動産に任せ下さい!


