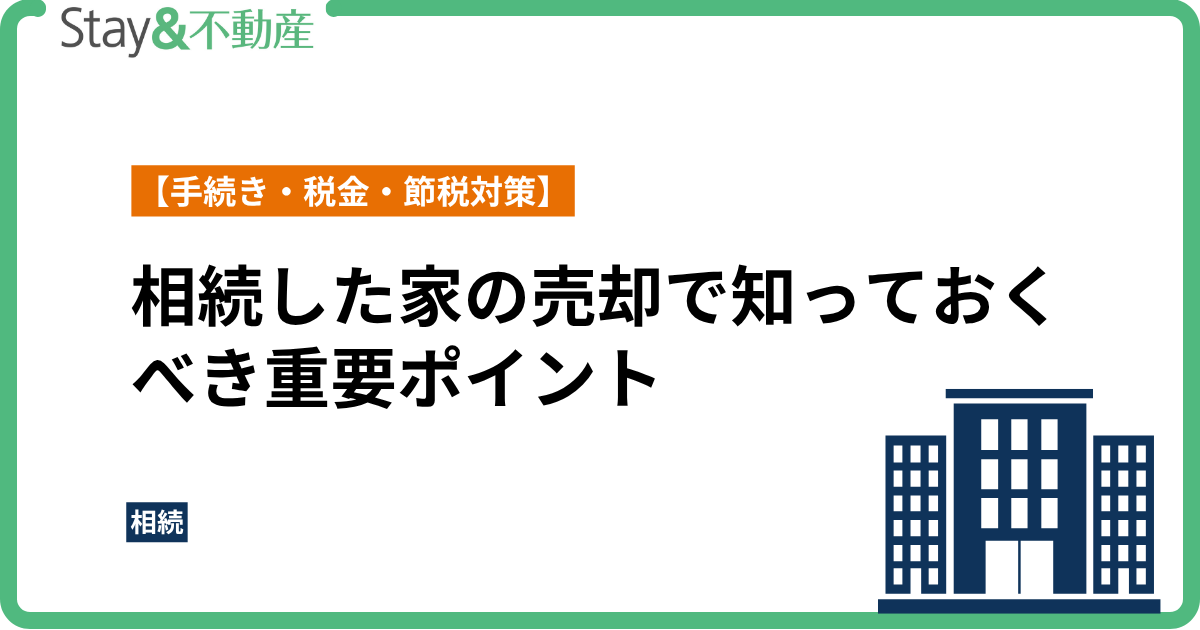相続した家を売却する際、手続きや税金についての知識が不足していると、予想外のトラブルや大きな税負担に悩まされることがあります。そこで、この記事では40代〜60代の方を対象に、相続した家を売却する際に必要な手続きや税金対策、節税方法を分かりやすく解説します。
相続に伴う家族間のトラブルを回避し、売却後にしっかりと利益を得るための重要ポイントを網羅していますので、ぜひ最後までお読みください。
相続した家を売却するべき?メリットとデメリットを比較
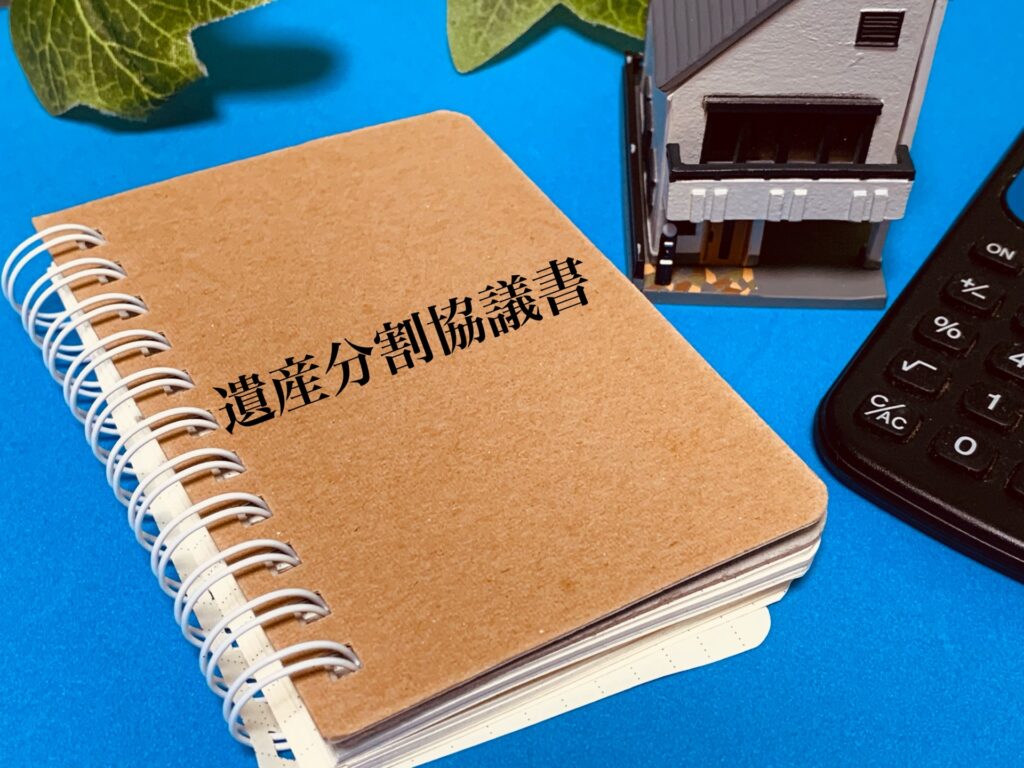
相続した家を売却するべきかどうかは、メリットとデメリットを比較して判断しましょう。家を維持するための管理コストを削減し、早期に現金化できる点一方、家族や親族との感情的な問題や、税金が発生するリスクなどの要素を踏まえて慎重に検討する必要があります。
相続した家を売却するメリット
相続した家を売却することには、以下の5つのメリットがあります。
- 資産の有効活用ができる
- 維持費の削減
- 資産を分割できる
- 節税対策になる
- 空き家問題の解消
1. 資産の有効活用ができる
相続した家を売却することで資産を現金化し、他の投資や生活費に充てることができます。そして、売却によって自由に資金を使えるようになる点は大きなメリットです。
2. 維持費の削減
家を所有していると、固定資産税や修繕費、管理費が必要です。
相続した家は特に、築年数が古い場合、維持費が高くつくことがあります。しかし、売却することでこれらのランニングコストを削減でき、余計な出費を避けることが可能です。
| 項目 | 売却後に削減できる費用例 |
|---|---|
| 固定資産税 | 約10万〜30万円/年 |
| 修繕・リフォーム費用 | 10万円〜数百万円 |
| 管理費(管理会社依頼時) | 5万〜20万円/年 |
3. 資産を分割できる
現金資産は不動産よりも分割しやすいため、相続財産を家族間で平等に分配するのが容易です。不動産をそのまま残す場合、のちに相続人間での意見の違いからトラブルが生じることがありますが、売却して現金にすれば公平な分割が可能です。
4. 節税対策として有効
相続税は、家を現金化した場合、売却利益に対して課税される「譲渡所得税」がかかるものの、基礎控除や特別控除、減税措置を活用することで、税負担を抑えることができます。。
5. 空き家問題の解消
相続した家を放置しておくと、いわゆる「空き家問題」として地域の防犯や景観に悪影響を及ぼすことがあります。売却することで、このようなリスクを回避し、地域社会にも貢献できます。
関連記事:
マンション 相続 売却 https://realestate.pro-reve.com/manshon-sale/inheritance/manshon-inheritance/
売却しない場合のデメリット:管理コストやトラブルリスク
相続した家を売却しない場合、いくつかのデメリットが生じます。維持コストや相続人間のトラブルリスクがその主な要素です。ここでは、家を売却せずに所有し続けた場合に考えられる5つの問題点を解説します。
1. 管理コストの増加
相続した家を維持するためには、前述のようにさまざまなコストがかかります。まず、固定資産税や都市計画税といった法的な税負担が定期的に発生します。また、建物の修繕やメンテナンスも必要不可欠です。
2. 空き家としてのリスク
売却せずに家を放置すると、空き家状態になる可能性があります。つまり空き家は防犯や防災上の問題を引き起こすだけでなく、放置が続けば「特定空き家」に指定されることもあります。
「特定空き家」に指定されると、税制優遇の適用外となり、固定資産税が最大6倍に増える可能性があります。さらに、空き家を放置しておくと、建物が老朽化し、倒壊のリスクも高まります。
関連記事:空き家買取業者おすすめ人気ランキング!選び方・買取相場 – つながり
3. 不動産価値の低下
売却しないまま家を所有し続けると、地域の市場環境や建物の劣化によって不動産価値が低下する可能性があります。なぜなら築年数が経過すればするほど、家の市場価値は下がり売却するタイミングを逃すと、最終的に売却額が大幅に減少してしまうこともあります。
さらに、家の老朽化が進むと売却自体が難しくなり、最終的には解体費用が必要になることも考えられます。
5. 節税対策の機会損失
相続した家を早めに売却することで、譲渡所得税の特別控除や減税措置を受けることができる場合があります。しかし、売却せずに家を保有し続けることで、これらの節税対策の機会を逃すリスクがあります。
例えば、家を売却する際に受けられる「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」を活用することで、譲渡所得税の負担を軽減できるケースがありますが、タイミングを逃すと適用を受けられない場合もあります。
関連記事:
資産価値のない家 相続 https://realestate.pro-reve.com/manshon-sale/worthless-house-inheritance/
家族や親族と相談する際のポイント

相続した家の売却を検討する際には、家族や親族との相談が非常に重要です。しかし相続には感情的な要素が絡むことが多いため、全員が納得のいく形で進めることが必要です。
1. 家族の想い出にこだわらない
相続した家は、家族にとって大切な想い出が詰まった場所であることが多いです。しかし、感情に流されてしまうと、冷静な判断ができなくなります。
特に、維持費や将来的な負担を考えた場合、想い出にこだわりすぎず、現実的な判断を優先することが重要です。思い出として残すのは写真や動画などをメインとし、空き家は活用するかお金に換えましょう。
2. 各相続人の立場を尊重する
家を相続する際、それぞれの相続人には異なる意見や状況があります。
例えば、家に住み続けたいと考える相続人がいる一方で、早急に売却して現金化したいと考える相続人もいるかもしれません。このような場合、全員の意見を尊重し、バランスを取りながら最良の選択肢を模索することが重要です。
3. 家の維持費や将来的なコストを共有する
家を相続した場合、売却するかどうかを判断するためには、家を残した場合の維持費や修繕費用、税金などのコストについて全員が理解している必要があります。
そこで、家族や親族に維持費の現状や将来的に必要なコストを具体的に提示することで、売却を進めるかどうかの判断がしやすくなります。
4. 共同名義のリスクとメリットを理解する
共同名義にはメリットとデメリットが存在します。相続人全員が家の所有権を持つため、公平に扱うことができる一方で家を売却したいと考える相続人がいても、全員の同意が得られない場合、売却が難しくなることがあります。
また、将来的な修繕費用や維持費を共同で負担する際にも、トラブルが発生するリスクがあります。
5. 家族全員での合意を優先する
家の売却や相続に関する決定は、家族全員が合意することが最も重要です。全員が同意していないまま売却や名義変更を進めると、後々トラブルに発展する可能性が高いため、時間をかけてでも全員の意見をしっかりと聞くことが大切です。
相続した家を売却するための手続きと必要書類のステップ

相続した家を売却する際には、まず不動産の名義変更(相続登記)を行い、その後に売却手続きを進める必要があります。名義変更には相続人全員の同意が必要で、相続登記や遺産分割協議書の作成が求められます。
また、売却時には相続関係説明図や遺産分割協議書などの書類も必要です。手続きをスムーズに進めるためには、事前に必要書類を確認し、タイミングを逃さないことが重要です。
不動産の名義変更から売却までの流れ
相続した家を売却するためには、まず不動産の名義を相続人に変更する必要があります。この相続登記が完了しなければ家の売却は進められません。
1. 相続人の確認と遺産分割協議
最初のステップとして、相続人全員を確認する必要があります。法定相続人は民法に基づいて決まります。そこで遺言書が存在する場合は、その内容に従うこともあります。相続人全員が集まり、遺産分割協議を行い、家の相続について合意を得ることが求められます。ここで重要なのは、相続人全員が合意しない限り、家を売却するための手続きを進めることができないという点です。
2. 相続登記の申請
相続人が確定し、遺産分割協議が完了したら、不動産の名義を変更する「相続登記」を行います。そして相続登記には、法定相続情報一覧図や遺産分割協議書、故人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書などが必要です。この手続きは、代表者が法務局に申請することで完了します。
また、住宅ローンの残債がある場合は、団体信用生命保険の手続き、あるいは残額の精算を行いましょう。相続登記と残債の清算が完了すると、相続人の名義で家を売却できる状態となります。
| 相続登記に必要な書類例 | 説明 |
|---|---|
| 法定相続情報一覧図 | 相続人を証明するための書類 |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員が家の相続について合意したことを示す書類 |
| 除籍謄本 | 故人の身分を証明するための書類 |
| 戸籍謄本 | 相続人の身分を証明するための書類 |
| 印鑑証明書 | 相続人が正式な書類に押印したことを証明する書類 |
3. 家の査定と売却準備
次に行うのは家の売却準備です。まず、不動産会社に家の査定を依頼し、市場価格を把握しましょう。査定が終わった後は、家を売却するための戦略を立てます。広告を出したり、内覧会を開いたりして購入希望者を集めるのが一般的です。また、売却時には家の状態を良好に保つため、必要な修繕や清掃、住宅検査などを行っておくことも大切です。
4. 売買契約の締結
購入希望者が見つかれば、売買契約を結びます。この際、不動産会社や司法書士のサポートを受けることをお勧めします。売買契約書には、売却価格、支払い方法、引き渡し日時、その他の条件が明記されます。売却契約が正式に締結されると、契約内容に基づいて家の引き渡しが行われます。
5. 売却後の手続きと税金申告
家を売却した後、売却益が出た場合には、譲渡所得税の申告が必要になります。また、売却益が大きい場合は、特別控除や減税措置を活用することで税負担を減らすことが可能です。税理士に相談し、適切な税金申告を行うことが大切です。
売却に必要な書類とその準備方法

相続した家を売却する際には、さまざまな書類が必要です。これらの書類を適切に準備し、スムーズな売却手続きを進めるためには、事前の確認が重要です。
1. 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
不動産登記簿謄本は、その家の所有者や権利関係を証明する重要な書類です。これは法務局で取得でき、相続登記が完了していることを確認するために必要です。登記簿謄本には、家の所在地や面積、権利関係が記載されているため、買主も安心して契約に進むことができます。
2. 相続関係説明図
相続した家を売却する際、相続関係説明図は相続人が誰であるかを示す書類です。これにより、相続が適正に行われていることが確認できます。たとえば法定相続人が複数いる場合には、全員の同意を得た上で家の売却を進める必要があります。相続関係説明図は、戸籍謄本や除籍謄本、遺産分割協議書と併せて準備します。
3. 遺産分割協議書
複数の相続人がいる場合、遺産分割協議書が必要です。この書類は、相続人全員が家の相続に関して合意したことを証明するもので、相続人全員の署名と押印が求められます。
4. 印鑑証明書
相続人の印鑑証明書は、売却手続きにおいて必要な書類です。印鑑証明書は、市区町村役場で取得でき、相続人が正式に売却に同意していることを証明するために使われます。印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものが有効とされているため、注意が必要です。
5. 固定資産税納税通知書
家の売却に際して、固定資産税の納税状況を確認するために固定資産税納税通知書が必要です。これにより、売却時点で未納の税金があるかどうかが確認できます。また、買主が固定資産税の負担を引き継ぐ場合があるため、売買契約書に直近の固定資産税額を明記する必要があります。
6. 身分証明書
売却の際、相続人全員の身分証明書が必要です。これは、本人確認のための書類であり、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどが使われます。身分証明書がないと契約が進められないため、売却手続き前に確認しておきましょう。
| 書類名 | 取得方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議書 | 相続人全員で作成 | 相続人全員の署名と押印が必要 |
| 印鑑証明書 | 市区町村役場で取得 | 発行から3ヶ月以内のものを使用 |
| 固定資産税納税通知書 | 市区町村からの通知 | 未納税額がある場合は売却前に清算 |
| 身分証明書 | 各相続人が個別で準備 | 免許証やマイナンバーカードなど |
7. 家の間取り図や設備仕様書
上記の書類のほかに、家の売却をスムーズに進めるために、家の間取り図や設備仕様書を準備しておくと、購入希望者にとっても安心です。これにより、家の状態や特徴を正確に伝えることができ、内覧時にも役立ちます。また、家のリフォーム履歴や設備の保証書がある場合は、それも併せて提供すると信頼度が増します。
専門家に依頼すべきタイミングとは?

相続した家の売却において、宅建士や司法書士、税理士といった専門家のサポートは重要です。特に相続や売却に伴う法的手続きや税務申告には専門的な知識が求められるためです。
1. 家の売却や残債の精算のタイミング
家を高く早く売ること、残債があればその清算を金融機関に掛け合うことには、宅建資格のある不動産会社スタッフのサポートを受けましょう。相続の状況を確認したうえで、最適な売却方法や、金融機関との話し合いのサポートをしてもらえます。
2. 名義変更(相続登記)のタイミング
相続登記は司法書士に依頼するのが一般的です。相続登記を行う際には、故人の除籍謄本や戸籍謄本、遺産分割協議書などの書類が必要となります。しかしこれらの準備や法務局への申請手続きは専門知識がないと難しいため、早い段階で司法書士に依頼することをお勧めします。
3. 節税対策や譲渡所得税の申告
相続した家を売却する際には、税金が大きな問題となります。特に売却益が発生した場合、譲渡所得税が課税されるため、これをどのように最小限に抑えるかが重要です。
税理士に依頼すれば、譲渡所得税の計算だけでなく、特別控除や節税対策の活用方法についてアドバイスを受けることができます。たとえば、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」を利用することで、売却益を大幅に軽減できるケースもあります。
4. 遺産分割協議が複雑な場合
相続人が複数いる場合、遺産分割協議が必要となります。この協議がスムーズに進まない場合や、相続人同士の意見が分かれる場合には、司法書士や税理士のサポートが有効です。特に、遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員の合意を得ることが重要であり、法的に有効な書類を作成するためには専門家の知識が不可欠です。
4. 譲渡所得税の申告タイミング
家を売却した後、売却益が発生した場合には譲渡所得税の申告が必要です。ここでも、税理士のサポートが役立ちます。税理士は適切な税金の計算や申告を行うだけでなく、控除や節税対策を最大限に活用して、税負担を軽減するためのアドバイスを提供します。また、相続に関連する税務上の注意点や、申告期限についても税理士から適切な指導を受けることができます。
売却時にかかる税金と控除の仕組みを知っておこう

相続した家を売却する際、譲渡所得税や相続税が発生します。譲渡所得税は家の売却益にかかり、控除を利用して節税が可能です。特に「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」などの控除が適用される場合、税負担を大幅に軽減できます。
また、相続税と譲渡所得税は別々に計算されるため、申告時には注意が必要です。税務手続きにおいては、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
相続税の計算方法
相続税は、相続した財産に対して課される税金で、家を相続する際にも適用されます。相続税の計算は、相続財産の総額から基礎控除を差し引き、そこから課税対象となる財産に税率を適用して計算します。ここでは、相続税の基本的な計算方法を詳しく解説します。
1. 相続財産の総額を把握する
相続税の計算の第一歩は、相続した家を含むすべての相続財産の総額を把握することです。相続財産にはたとえば家、不動産、現金、預貯金、株式、生命保険金などが含まれます。家の場合、その評価額は「路線価」や「固定資産税評価額」を基に計算されることが一般的です。財産全体の評価額を合計した金額が、相続税の計算基礎となります。
2. 基礎控除を差し引く
相続税には一定の基礎控除額が設定されており、この金額は相続人の人数によって変動します。基礎控除額の計算式は次の通りです:
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数
たとえば、法定相続人が2人の場合の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円」となります。この基礎控除額を相続財産の総額から差し引いた後の金額が、相続税の課税対象額となります。
3. 課税対象額に税率を適用する
課税対象額が確定したら、次にその金額に応じて相続税率を適用します。相続税の税率は、相続財産の金額によって異なり、10%から最大55%までの累進課税方式が採用されています。以下の表は、課税対象額に応じた相続税率の一覧です。
| 課税対象額(相続財産の総額 – 基礎控除) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
4. 相続税の計算例
次に、具体的な計算例を見てみましょう。
例:
- 相続財産の総額:7,000万円
- 法定相続人の人数:3人
- 基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
- 課税対象額:7,000万円 – 4,800万円 = 2,200万円
課税対象額2,200万円に対して、税率は15%(3,000万円以下の範囲)となり、控除額は50万円です。したがって、課税額は以下のようになります。
相続税額 = 2,200万円 × 15% - 50万円 = 280万円
この場合、相続税として280万円を支払う必要があります。
5. 節税対策を考える
相続税の負担を軽減するためには、適切な節税対策が必要です。たとえば、家を相続する際には「小規模宅地等の特例」を活用することで、相続税評価額を最大80%まで減額できる場合があります。この特例を利用するためには、相続人がその家に一定期間居住するなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
譲渡所得税の計算方法

相続した家を売却する際には、「譲渡所得税」が発生します。譲渡所得税は、家を売却した際の利益(譲渡所得)に対して課せられる税金です。家を相続して売却する場合でも、この譲渡所得税の計算方法は通常の不動産売却と同じで、譲渡所得に対して課税されます。
1. 譲渡所得の計算方法
譲渡所得税を計算するためには、まず譲渡所得(売却益)を求める必要があります。譲渡所得は、次の計算式で算出されます。
譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)
- 売却価格:
家を売却した際の売却額です。 - 取得費:
家を購入したときの価格や、その後のリフォーム費用などが含まれます。たとえば相続した家の場合、故人が購入した価格を「取得費」として計上します。もし購入価格が不明な場合、売却価格の5%を取得費として計算する「概算取得費」が適用されます。 - 譲渡費用:
家を売却する際にかかった仲介手数料や、測量費、解体費用などです。
2. 譲渡所得税の税率
譲渡所得に対する税率は、不動産の保有期間に応じて異なります。家を相続して売却する場合でも、故人が家を取得した日からの年数が保有期間に含まれます。
- 短期譲渡所得(保有期間が5年以下):39.63%(所得税30% + 住民税9% + 復興特別所得税0.63%)
- 長期譲渡所得(保有期間が5年超) :20.315%(所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315%)
3. 譲渡所得税の計算例
次に、具体的な計算例を見てみましょう。
例:
- 売却価格:4,000万円
- 取得費(購入時の価格):2,000万円
- 譲渡費用:200万円
- 保有期間:10年(長期譲渡所得に該当)
譲渡所得の計算:
まず、売却の際の差益を計算します。
譲渡所得 = 4,000万円 - (2,000万円 + 200万円) = 1,800万円
譲渡所得税の計算:
譲渡所得が長期譲渡所得に該当するため、税率は20.315%となります。
譲渡所得税 = 1,800万円 × 20.315% = 約366万円
この場合、譲渡所得税は366万円となります。
4. 譲渡所得税を軽減するための特例
譲渡所得税は非常に大きな税負担になるため、節税対策として「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」などの特例を利用することが重要です。この特別控除を利用すれば、譲渡所得から最大3,000万円が控除され、税額を大幅に軽減できます。しかし特別控除を適用するためには、一定の条件を満たす必要があります。
特別控除適用後の計算例:
上記の例で「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が適用される場合、譲渡所得は以下のように計算されます。
譲渡所得 = 1,800万円 - 3,000万円 = 0円(この場合、譲渡所得税は発生しません)
この特例を適用すれば、税額が大幅に減少またはゼロになります。
5. 譲渡所得税の申告方法
家を売却した後、譲渡所得税は確定申告で申告します。通常、売却した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行い、税務署に提出します。譲渡所得の計算に誤りがあると過剰な税金を支払うことになるため、正確な計算と申告が必要です。
また、特別控除などを利用する場合は、所得税が発生しなくとも確定申告を行い、申告書にそれらの内容を明記する必要があります。
相続した家を売却するときの特別控除や減税措置の活用法

相続した家を売却する際には、税負担が大きくなることが心配されますが、適切な特別控除や減税措置を活用することで、大幅に税金を軽減することが可能です。ここでは、相続した家の売却に際して知っておくべき特別控除や減税措置について詳しく解説します。
1. 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
譲渡所得税の負担を軽減するために最も代表的な特例が、前述の「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。この控除を利用することで、譲渡所得(売却益)から最大3,000万円が差し引かれ、課税対象となる金額を大幅に減らすことができます。
2. 贈与を活用した節税対策
家を相続してすぐに売却するのではなく、贈与という手段を利用することでも節税効果が期待できます。相続人間で相続する家を分割する場合、贈与税の課税対象となる可能性がありますが、相続時精算課税制度を活用することで、贈与税を最大限に控除することが可能です。
相続時精算課税制度とは
60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫に対して贈与を行う際、2,500万円までの贈与税を控除できる制度です。この制度を活用すれば、贈与税の負担を抑えつつ、家の相続をスムーズに進めることができます。
ただし、相続時精算課税制度を利用する場合、後に相続税がかかることになるため、事前に税理士と相談することが重要です。
3. 小規模宅地等の特例
相続した家が被相続人(亡くなった方)の居住用宅地であった場合、「小規模宅地等の特例」を利用することで、相続税の評価額を大幅に減額することができます。この特例を活用することで、相続税の評価額を最大で80%減額できるため、大幅な節税効果が期待できます。
小規模宅地等の特例・適用条件
- 相続人がその家に引き続き居住している場合。
- 相続人がその家を売却する場合、特例を受けた後に適用することも可能。
このほかにも適用条件が細かく規定されているので、事前にしっかり確認しておきましょう。
4. 減税措置を活用するための準備
各種の控除や減税措置を適用するためには、申告の際に必要な書類や証明書をしっかりと準備することが大切です。
減税措置の種類とまとめ
| 減税措置 | 主な適用条件 | 控除額・効果 |
|---|---|---|
| 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例 | 自分や親族が居住用として利用していた場合 | 譲渡所得から最大3,000万円を控除 |
| 小規模宅地等の特例 | 相続人が引き続き居住している場合 | 相続税評価額が最大80%減額 |
| 相続時精算課税制度 | 60歳以上の親から20歳以上の子への贈与 | 最大2,500万円の贈与税控除 |
相続した家の売却で知っておくべきQ&A

相続した家を売却する際の手続き、税金、節税対策など、相続した家の売却に関するよくある質問とその回答をQ&A形式で解説します。
Q1. 相続した家を売却する際の主な手続きは何ですか?
相続した家を売却するための手続きは以下の通りです。
- 相続登記
最初に不動産の名義変更を行い、故人の名義を相続人の名義に変更します。 - 遺産分割協議
相続人間で家の分割方法を話し合い、他の遺産と合わせて遺産分割協議書を作成します。 - 家の査定と売却準備
不動産会社に査定を依頼し、売却価格を決定します。 - 売買契約と引き渡し
購入希望者が見つかれば、売買契約を結び、売却手続きが完了します。
Q2. 相続した家の売却には税金がかかりますか?
はい、相続した家を売却する際には、主に2種類の税金がかかります。
- 譲渡所得税
家を売却して利益が出た場合、譲渡所得税が発生します。売却益に応じて、長期譲渡所得(5年超保有)なら20.315%、短期譲渡所得(5年以下保有)なら39.63%の税率が適用されます。 - 相続税
家を相続する際に相続税が発生している場合があります。売却することで新たな相続税が発生するわけではありませんが、相続時に支払った相続税を取得費に加算する「取得費加算の特例」が利用できる場合があります。
Q3. 特別控除を受けることはできますか?
相続した家を売却する際、一定の条件を満たせば「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が適用されます。この特別控除により、譲渡所得から最大3,000万円を控除でき、譲渡所得税の負担を大幅に軽減できます。主な適用条件は以下の通りです。
- 売却する家が故人の居住用財産であったこと。
- 売却が相続開始後3年以内に行われること。
- 賃貸していた場合や事業用に利用していた場合は、適用外となることが多いです。
Q4. 売却を進める際、税理士や司法書士に依頼するタイミングは?
専門家に依頼するタイミングは次のような場合です。
- 司法書士
相続登記の手続きや遺産分割協議書の作成をサポートします。早い段階で司法書士に依頼しておくと、スムーズに手続きを進められます。 - 税理士
譲渡所得税や相続税の計算、特別控除の適用など、税務上の複雑な処理が必要な場合、税理士に相談するのが賢明です。売却益が発生する場合や節税対策を検討する際には、税理士のサポートが重要です。
Q5. 相続した家を売却しない場合、どのようなリスクがありますか?
相続した家を売却せずに放置すると、以下のリスクが考えられます。
- 固定資産税や維持費
相続後も家の維持には費用がかかり続けます。特に、古い家の場合は修繕費がかさむこともあります。 - 空き家問題
家を長期間放置しておくと、空き家問題として防犯や防災の観点から問題視されることがあります。老朽化した場合、解体費用も発生します。 - 家族間のトラブル
相続人が複数いる場合、家の管理や利用方法を巡ってトラブルが発生することがあります。
Q6. 相続した家を賃貸に出すことはできますか?
相続した家を賃貸に出すことは可能です。しかし、賃貸に出す場合、賃貸収入に対して所得税が課されるため、確定申告が必要です。また、賃貸することで「3,000万円の特別控除」が適用できなくなる可能性があるため、賃貸に出すか売却するかの選択は慎重に検討する必要があります。
まとめ

相続した家を売却する際には、手続きや税金、家族間の調整が必要で、複雑なプロセスに直面します。本記事では、売却のメリット・デメリット、必要書類や節税対策をわかりやすく解説しました。
特に、税金負担を減らす方法や法的なミスを防ぐための知識は、スムーズな売却を進めるために重要です。正しい知識を持って、家の売却に伴う不安を解消してください。
相続した家の売却も、Stay&不動産にご相談ください!
スムーズな相続のために、家を素早く売却して換価分割したいケースもあります。Stay&不動産では相続人の方のニーズに応じた買取のお手伝いをさせて頂きます。