住宅ローンを借り換える際の主な目的は、返済総額を減らすことでしょう。しかし、借り換えの際には元の住宅ローンと新しい住宅ローンでそれぞれ手数料などの諸費用が発生します。
借り換えの際には、良い条件の新しい住宅ローン商品を探すだけでなく、諸費用を安く抑えることが大切です。借り換えの際にはぜひこの記事を参考にしてください。
住宅ローン借り換え手数料の基本知識

住宅ローンの借り換えは、利息を節約し総返済額を減らす大きなチャンスです。しかし、借り換えには手数料が発生し、その相場や内訳を理解することが重要です。
その金額は数万円から数十万円と幅広いです。手数料は借り換えのメリットを最大化するための重要な要素であり、事前に相場を調べ、コストを抑える対策を取ることが、借り換えの成功につながります。
住宅ローンの借り換えを検討する際、さまざまな手数料が発生します。以下に、住宅ローンの借り換え時に一般的に発生する5つの手数料を紹介します。
1. 事務手数料
住宅ローンの借り換え手続きを行う金融機関に支払う「事務手数料」は、借り換えに伴う書類作成や事務作業にかかるコストです。
相場は金融機関によって異なりますが、3万円〜5万円程度が一般的です。一部のネット銀行では、住宅ローン金額の一定割合(例:1〜2%)を手数料として請求する場合もあります。
2. 登記費用
住宅ローンの借り換えには、担保の債権者の変更に伴う登記手続きが必要です。この登記費用には、司法書士への報酬と、法務局へ支払う「登録免許税」が含まれます。
登録免許税は借り換え金額の0.4%が通常の相場です。また、司法書士への報酬としては、5万円〜10万円が相場です。
3. 印紙税
契約書を作成する際に必要な「印紙税」は、借り換え後の住宅ローン契約書にも適用されます。印紙税は借り換えの金額によって異なりますが、通常は1万円〜2万円が発生します。
4. 保証料
新しい住宅ローンに保証人を付ける場合、保証会社に支払う「保証料」も借り換え時の費用として計上されます。
保証料の相場は、借り換え金額の0.2%〜0.5%ですが、金利に上乗せして支払う形が多いでしょう。また、保証料を支払わないプランを提供している金融機関もあるため、自分に合った融資条件を比較することが重要です。
5. 火災保険料の更新費用
住宅ローンの借り換えに際して、火災保険の契約が必要になる場合があります。新しい金融機関での住宅ローン契約に合わせて、火災保険の更新を行うケースでは、地震保険も合わせて数万円〜10万円程度が相場の費用がかかることがあります。
主な手数料の一覧表
| 手数料の種類 | 内容 | 相場 |
|---|---|---|
| 事務手数料 | 金融機関の事務処理費用 | 3万円〜5万円 |
| 登記費用 | 登記変更に伴う費用(司法書士報酬+登録免許税) | 5万円〜10万円 + 借り換え金額の0.4% |
| 印紙税 | 住宅ローン契約書に必要な税金 | 1万円〜2万円 |
| 保証料 | 保証会社への支払い費用 | 借り換え金額の0.2%〜0.5% |
| 火災保険料の更新費用 | 新しい住宅ローンに合わせた火災保険の更新 | 数万円〜10万円 |
これらの諸費用は住宅ローンの借り換えを行う際の重要な要素で、特に手数料や登記費用などは、総額に大きな影響を与えます。したがって、借り換えを検討する際は、これらの諸費用の概算や相場を事前にしっかりと把握し、総合的なコスト計算を行うことが、借り換えを成功させるためのポイントとなります。
金融機関別の手数料比較

住宅ローンの借り換えにおいて、手数料は金融機関によって大きく異なります。
主要銀行では、事務手数料が3万円から5万円程度ですが、ネット銀行では住宅ローン残高の1〜2%が手数料として設定されることが多いです。低金利プランを提供するネット銀行を利用することで、総合的なコスト削減が期待できます。
主要銀行とネット銀行の手数料を徹底比較
住宅ローンの借り換え時にかかる手数料は、金融機関によって大きく異なります。特に、主要銀行とネット銀行ではその差が顕著であり、借り換えによる節約効果を最大化するためには手数料の相場を比較することが重要です。
ここでは、主要な銀行とネット銀行の手数料を徹底比較してみましょう。
1. 事務手数料の比較
住宅ローンの借り換え手続きにかかる「事務手数料」は、金融機関ごとに異なります。
主要銀行では、事務手数料が借入金額の2.2%が一般的です。一方で、ネット銀行では同様に借入金額の2.2%が相場ですが、定額型の手数料を採用している場合もあります。たとえば、新生銀行では事務手数料が定額5万5000円、楽天銀行では33万円といった固定費用を設定している場合もあります。
2. 保証料の比較
保証料は、住宅ローンを借り換える際のもう一つの大きなコストです。多くのネット銀行では、住宅ローンの保証料が無料のケースが一般的です。これに対し、主要銀行では保証料が必要な場合があり、借入金額に応じて数十万円の保証料がかかることもあります。例えば、みずほ銀行では、保証料が借入金額に応じて変動するプランや、金利に上乗せするタイプが選択可能です。
3. 繰上返済手数料
借り換え後に繰上返済を検討する際には、繰上返済手数料も重要です。多くのネット銀行では、繰上返済手数料が無料であることが特徴です。これに対して、主要銀行では数千円から数万円の手数料がかかることが多いです。
主要金融機関の手数料比較表
| 金融機関 | 保証料 | 事務手数料 | 繰上返済手数料 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 無料 | 借入額×2.2% | 5,000円~30,000円 |
| みずほ銀行 | 借入額により変動 | 無料 | 5,000円~30,000円 |
| 新生銀行 | 無料 | 5万5000円または借入額×2.2% | 無料 |
| 楽天銀行 | 無料 | 33万円 | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 無料 | 借入額×2.2% | 無料 |
住宅ローンの借り換えにおいて、主要銀行とネット銀行の手数料を比較することで、自分に合ったプランを選ぶことが可能です。
ネット銀行は、保証料や繰上返済手数料が無料の場合が多く、住宅ローンの初期コストを抑えたい方にはおすすめです。主要銀行でも手数料が低いプランを提供しているケースがあるため、全体のコストを総合的に比較しながら判断することが大切です。
手数料が安い金融機関の選び方

住宅ローンの借り換えを検討する際、手数料が安い金融機関を選ぶことは重要なポイントです。手数料が低ければ、借り換えによる利息の節約効果がより大きくなり、総返済額の削減につながります。ここでは、手数料が安い金融機関の選び方について詳しく解説します。
事務手数料と保証料の確認
住宅ローン借り換え時にかかる代表的な費用には、「事務手数料」と「保証料」があります。
事務手数料は、借入金額に応じた定率型(借入額×2.2%)や、定額型(3万円〜5万円程度)があり、金融機関によって相場が異なります。特にネット銀行では、事務手数料が安いか、保証料が無料になるプランが多く見られます。
一方、保証料は借り換え時に一括で支払う場合と、金利に上乗せされて月々支払う場合があります。保証料がかからない金融機関もありますが、その場合は他の手数料が高くなることもあります。たとえば、みずほ銀行では保証料を前払いするプランもあり、選択肢が広がっています。
ネット銀行と主要銀行の比較
前述のようにネット銀行は一般的に手数料が安いことで知られています。事務手数料や繰上返済手数料が無料であることが多く、借り換えを検討する際には注目ポイントですです。一方、主要銀行との比較は、適用金利や保証料とのバランスを見て総合的に判断することが必要です。
シミュレーションサイトの活用
住宅ローン借り換えの手数料を比較する際は、金融機関のシミュレーションサイトを活用しましょう。借入金額や返済期間を入力することで、実際にかかる手数料や金利を試算できます。これにより、複数の金融機関のプランを簡単に比較でき、自分に合った最適な借り換えプランを見つけやすくなります。
キャンペーンや割引活用
金融機関では、住宅ローンの借り換えキャンペーンを実施していることがあります。これらのキャンペーンでは、事務手数料の割引や、保証料が無料になる場合があります。事前に確認し、これらのキャンペーンをうまく活用することで、借り換えにかかる費用を大幅に削減できる可能性があります。
コストを抑えるための裏技や方法
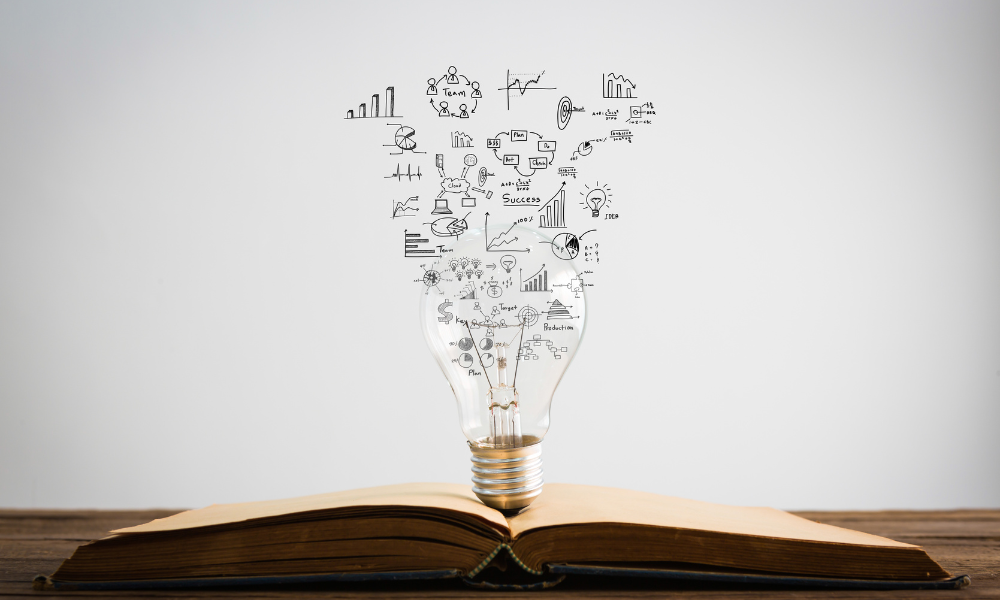
住宅ローンの借り換えは、総返済額の節約が期待できる一方で、手数料や諸費用が発生します。そのため、手数料が安い金融機関を選ぶだけでなく、そのほかの部分でコストを抑える方法を知っておくことも重要になります。
以下では、借り換え時の手数料を抑える裏技や方法を紹介します。
1. 優遇金利を利用する
金融機関によっては、住宅ローンの借り換え時に優遇金利が適用されるケースがあります。この優遇金利は、適用条件を満たすことで通常よりも低い金利で借り換えが可能になるため、結果的に総支払額の大幅な削減が期待できます。
たとえば、自己資金をある程度用意できる場合や、長期優良住宅などの特定条件を満たす物件の場合に優遇金利が適用されることがあります。
2. 自己資金を活用して手数料を減らす
住宅ローン借り換えの際には、自己資金を一部用意することで、借入額を減らし手数料を抑える方法があります。借入金額が少なくなるほど、手数料や保証料が低減されるため、自己資金を活用することでトータルコストを削減できます。
3. 金利上乗せ型プランを選ぶ
一部の金融機関では、手数料を削減する代わりに金利を若干上乗せする「金利上乗せ型」のプランを提供しています。この方法では、初期の手数料負担を軽減できるため、手元資金に余裕がない方や、手数料負担を抑えたい方におすすめです。
ただし、借り換えのほうが損とならないように、トータルでの収支はよく検討しましょう。
借り換え手数料を抑えるための5つのポイント

住宅ローンの借り換え手数料を抑えるためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。総返済額と手数料の相場を比較して最もコスト効果の高いプランを選ぶことが重要となります。
以下に、手数料やその他の費用を抑えるための具体的なコツを紹介します。
1. ネット銀行を活用
冒頭でも申し上げましたが、ネット銀行は、従来の銀行に比べて手数料が低いことが多く、借り換えにおいて大きなメリットがあります。
ネット銀行では事務手数料が定額で設定されているか、従来の銀行に比べて低い相場で設定されていることが一般的です。さらに、保証料が無料になるプランを提供しているネット銀行も多く、総合的なコスト削減が可能です。
2. 優遇金利を活用
借り換え時に優遇金利を利用できる場合、金利が低く設定されているプランを選ぶことで、長期的な返済負担を減らすことができます。優遇金利は金融機関によって条件が異なり、例えば長期優良住宅や一定の自己資金を用意することで適用されることがあります。
また、期間限定のキャンペーンによって、さらに低金利での借り換えが可能になる場合もあるため、事前に情報を確認し、できるだけ有利な条件で借り換えを行うことが重要です。
3. 自己資金を活用して手数料を削減
自己資金を一定額用意できる場合、借入額を減らすことで、発生する手数料を抑えることが可能です。特に、借入額に応じて変動する「事務手数料」や「登記費用」は、借入額が小さくなるほど比例して減少します。
例えば、借入額を少し減らすだけで、事務手数料や保証料が数万円単位で節約できる場合があります。これにより、自己資金をうまく活用して初期費用を軽減することができます。
4. キャンペーンや割引を利用
多くの金融機関では、住宅ローンの借り換えに際してキャンペーンや割引を実施していることがあります。これらのキャンペーンでは、手数料が一部免除されたり、優遇金利が適用されたりすることがあります。
金融機関ごとの最新情報を常にチェックし、借り換えのタイミングを見計らうことも、諸費用を相場よりも抑える有効な手段です。
5. 繰上返済のタイミングに注意
返済が進んでいる場合は利子の節約よりも各種手数料が多額で、「繰り上げ返済のメリットがない=そのまま最後まで毎月返済したほうが得」というケースもあります。金融機関の担当者が教えてくれますが、注意しましょう。
住宅ローンの借り換えを成功させるための金融機関の選び方

住宅ローンの借り換えを成功させるためには、借り換えによって得られる利子分の節約や総返済額の減少を最大化するため、金融機関の手数料や金利の相場をしっかり比較し、最適な選択をする必要があります。
ここでは、住宅ローンの借り換えを成功させるための金融機関の選び方について解説します。
手数料の比較
借り換えを検討する際、まず重要になるのが手数料の比較です。各金融機関では、事務手数料や保証料、繰上返済手数料などが異なります。
特にネット銀行では、事務手数料が定額で設定されているケースが多く、総コストを抑えるのに有効です。例えば、楽天銀行や住信SBIネット銀行では事務手数料が「借入額×2.2%」と定率型ですが、保証料は無料で提供されています。
| 金融機関 | 事務手数料 | 保証料 | 繰上返済手数料 |
|---|---|---|---|
| 楽天銀行 | 33万円 | 無料 | 無料 |
| 新生銀行 | 5万5000円または借入額×2.2% | 無料 | 無料 |
| 住信SBIネット銀行 | 借入額×2.2% | 無料 | 無料 |
手数料が無料の金融機関もありますが、その分金利が高く設定されている場合があるため、手数料と金利を相場などと総合的に比較して判断することが大切です。
金利プランの比較
金融機関を選ぶ際は、提供されている金利プランも重要な要素です。借り換え時に、固定金利と変動金利のどちらが最適かを考慮し、自分に合ったプランを選ぶことが大切です。
特に、金利変動リスクを避けたい場合は、固定金利が安定した返済計画を立てやすい選択肢となります。一方、低金利環境を利用したい場合は、変動金利を選ぶことが有利な場合もあります。
また、一部の金融機関では優遇金利が適用されることもあります。
例えば、一定の条件(自己資金が一定額以上ある、あるいは長期優良住宅を所有しているなど)を満たすと、通常よりも低い金利が適用される優遇プランが用意されています。このような優遇金利の活用により、総返済額を大幅に減らすことが可能です(借り換え手数料参考)。
借り換え手数料を抑えるために注意すべきこと

住宅ローンを借り換える際、手数料を抑えることが大きな節約につながりますが、注意するべきこともあります。以下では、手数料を抑える際に見落としがちなポイントや注意すべき点について詳しく解説します。
1. 総コストを把握する
住宅ローンの借り換えを検討する際、手数料だけに注目せず、総コストをしっかりと把握することが重要です。借り換えによって利息の節約が見込まれる一方で、借り換えに伴う事務手数料や保証料、登記費用などが発生します。
事務手数料は金融機関によって異なり、借入額に対して2.2%などの相場で設定されるケースが多いですが、定額制のところもあります(借り換え手数料参考)。借り換えにかかる初期費用と、その後の利息の削減効果をしっかり比較することが大切です。
2. 手数料無料プランのリスクを理解する
一部の金融機関では、「手数料無料」のプランが用意されていますが、このようなプランには注意が必要です。手数料無料の代わりに、金利が高く設定されていることがあり、結果的に総返済額が増加する可能性があります。
特に、長期的に借り換えを行う場合は、金利の上昇リスクを考慮する必要があります。短期的な手数料削減にこだわりすぎず、金利や総支払額全体を見据えた判断が求められます。
3. 繰上返済の手数料に注意
借り換え後に繰上返済を考えている場合、繰上返済手数料にも注意が必要です。多くのネット銀行では繰上返済手数料が無料となっていますが、主要銀行では数千円から数万円の手数料がかかることがあります。
繰上返済を検討している場合は、手数料が無料の金融機関を選ぶことで将来的なコストを抑えることができます。
4. キャンペーンや割引をチェックしておく
多くの金融機関では、住宅ローン借り換え時にキャンペーンや割引が実施されています。これらのキャンペーンでは、事務手数料の一部が免除されたり、優遇金利が適用されたりすることがあります。
キャンペーンを利用することで、借り換え時の初期費用を大幅に削減できるため、事前に各金融機関のキャンペーン情報をチェックしておくことが重要です(借り換え手数料参考)。
住宅ローン借り換えの手数料相場とは?コストを抑えるポイントのQ&A

住宅ローンの借り換えは、利息の節約や総返済額の減少を期待できる有効な手段です。しかし、借り換えにかかる手数料も無視できない要素です。ここでは、借り換え手数料の相場やコストを抑えるポイントについて、Q&A形式で解説します。
Q1. 住宅ローン借り換え時にかかる手数料の相場はどれくらいですか?
住宅ローンを借り換える際には、複数の手数料や諸費用が発生します。一般的に発生する主な手数料は以下の通りです。
- 事務手数料
借入額に対して定率(例:2.2%)または定額(3万円〜5万円)がかかることが多いです。ネット銀行では定額制を採用していることが多く、総コストを抑えやすいです。 - 保証料
保証料は借入額の**0.2%〜2%**程度が相場です。ネット銀行では保証料が無料の場合が多く、借り換えの際のコストを抑えることができます。 - 登記費用
登記変更に伴う司法書士の報酬や登録免許税がかかります。5万円〜10万円程度の費用が一般的です。 - 印紙税
契約書に必要な印紙税は、借入額によって異なり、1万円〜2万円程度です。
Q2. 借り換えによる利息の節約はどのくらい期待できますか?
借り換えによる利息の節約額は、借入金額、残りの返済期間、金利差によって異なります。
たとえば、金利が1%下がるだけで、数百万円単位の節約が期待できることもあります。ただし、手数料や諸費用を差し引いた後でも、十分にメリットがあるかどうかを確認するために、借り換え前後の総返済額をシミュレーションすることが重要です。
Q3. 借り換え手数料を抑えるための方法はありますか?
借り換え手数料を抑えるためには、以下のようなポイントに注意すると良いでしょう。
- ネット銀行を活用する
ネット銀行では、事務手数料や保証料が安く設定されていることが多く、総コストを大幅に抑えることができます。例えば、楽天銀行や住信SBIネット銀行では、事務手数料が定額制、保証料が無料となっており、初期コストを低く抑えられます。 - キャンペーンを活用する
多くの金融機関では、借り換え時に手数料や金利が割引されるキャンペーンを実施しています。タイミング良くキャンペーンを利用することで、手数料や金利を大幅に削減することができます。 - 優遇金利を狙う:一定の条件を満たすことで、優遇金利が適用されるケースがあります。たとえば、自己資金を一定額以上用意する、長期優良住宅を購入するなど、条件を満たすことで金利が低くなることがあり、総返済額を抑えることが可能です。
Q4. 手数料が安い金融機関を選ぶにはどうすれば良いですか?
手数料が安い金融機関を選ぶには、複数の金融機関を比較することが大切です。各金融機関は異なる手数料体系を持っているため、事前にシミュレーションツールを活用し、具体的な手数料と総返済額を試算することが有効です。
また、事務手数料が無料のプランを選択する場合は、金利に上乗せされる可能性があるため、金利と手数料のバランスを考慮した選択が求められます。
Q5. 借り換え時に注意すべきポイントは?
借り換えのメリットを最大限に活かすためには、以下のポイントにも注意が必要です。
- 繰上返済手数料の確認
借り換え後に繰上返済を行う予定がある場合は、その手数料が無料かどうかを確認しましょう。ネット銀行では、繰上返済手数料が無料であることが多く、コストを抑えることができます。 - 総コストの把握
借り換えによる利息の節約効果があっても、手数料や諸費用を含めた総コストが増える場合もあります。事前にシミュレーションを行い、手数料を含めた総支払額を正確に把握することが重要です。
まとめ

住宅ローンの借り換えは、手数料や諸費用を理解するところから始まります。手数料の相場や金融機関ごとの比較を事前に把握し、優遇金利やキャンペーンを活用しましょう。マイナス金利政策の解除で、今後利上げが想定されるという風潮ですが、金融機関の間では、激しい顧客獲得競争が行われています。
家計の見直しを検討している30代から50代の方々にとって、最適な借り換えプランを選ぶことは、将来の経済的な安定をサポートする重要な選択肢です。
家の売却をお考えの方は、どんなことでもStay&不動産へご相談ください!


